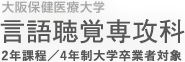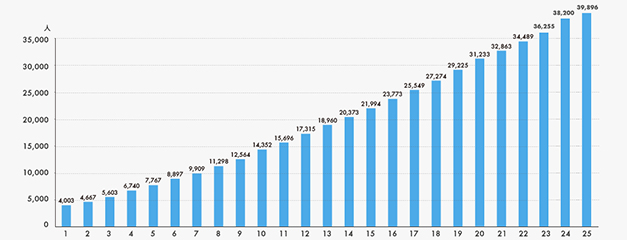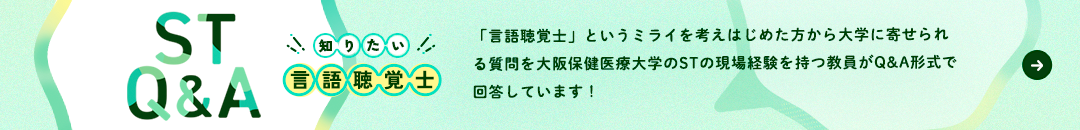INTRODUCTION
「人の役に立つ言語聴覚士の輩出」を掲げる大阪保健医療大学 言語聴覚専攻科では、言語聴覚士資格を持つ臨床経験豊富な教員のほかに、第一線で活躍する研究者も教鞭を執る。音響学や心理学を背景に基礎研究に携わる松井 理直(まつい みちなお)教授もその一人だ。
私たち人間が音声を通じて意思疎通を図るためには、音を聞き分け、ことばとして認識し、意味を理解することと合わせて、音声に意味や感情を載せて発することが求められる。微妙な音の強弱や周波数の高低差で感情を表現する発話コミュニケーションは、科学的に見てもきわめて高度なことをおこなっていると松井教授は話す。
松井教授は、このメカニズムの研究を通じて新たな笛式人工喉頭の開発や、発話することが難しい患者の年齢や感情に適した人工音声の設計などさまざまな応用研究にも取り組んでいる。臨床現場で得られた経験が自身の研究活動に大きな影響を与えたと語る松井教授に、声とコミュニケーションの研究について伺った。
ことばのメカニズムとシミュレーション
──松井教授は発話のメカニズムに関する研究や人工合成音声などのツール開発に取り組んでいらっしゃいますが、そのルーツはどこにあるのでしょうか。
音声研究の歴史は長く、18世紀から19世紀にかけて欧米でおこなわれた発話行為を模倣する機械の開発とともに発展してきました。人間の声を模倣しようとあらゆる方法が試されていますが、当時は肺や喉、口、声帯といった発声器官の形態と動作をまねるところから始まりました。人間の体よりも単純な構造をした彫刻や機械を用いた実践が、今日の工学や物理学、心理学など広範囲な分野を体系化した音響学へとつながっています。
学生時代に私が所属していた研究室では、人工喉頭の研究をおこなっていましたが、人間の喉は非常に複雑な構造をしており、当時最先端のコンピュータを使ってもシミュレーションすることが困難でした。そこで、人の「話し声」をまねることができるオウムや九官鳥といった鳥の喉に注目し、人間よりも単純な喉の構造でどのように声を再現しているのかというテーマで研究に取り組んでいました。今と比べると当時のコンピュータは性能が低かったこともあり、音とは何か、数学的な性質の違いがどこに現れるのかといった現象そのものに向き合っていたように思います。
その後、大阪保健医療大学では、口を動かさずに「カカカカカ」と発話するメカニズム(調音運動)の解明や、数理モデルを用いたシミュレーションや定量的な評価に関する研究などに取り組んでいます。


ことばを失った患者と言語聴覚士
━━研究を始められた当時は、音声の原理やメカニズムが研究の中心だったのですね。その後、人間の音声や言語そのものを研究対象とするなかで、言語聴覚士や患者さんと関わる機会はあったのでしょうか

研究者として人工喉頭の研究に取り組む中で、ある患者さんとの出会いが大きな転機となりました。言語聴覚士の友人から、筋萎縮性側索硬化症(ALS)[*1] 患者のリハビリについて相談を受けたのです。彼は「症状の進行が早く、患者さんのリハビリに対するモチベーションを保つことが難しい」と言うのです。ALSは不治の病です。病気の進行とともに筋力が衰えていき、その結果コミュニケーション手段も限定的になってしまいます。当初は患者さんが発音のメカニズムを学ぶことで最低限の発話ができはないかと考えていたのですが、残念ながら症状の進行が早くそれは叶わないことが分かりました。
次に注目をしたのが、合成音声を用いたコミュニケーションです。現在ではコンピュータやタブレット端末の性能の進化に伴い、視線を動かして文字を入力し、機械がそれを比較的自然に読み上げることができます。しかし、当時の人工合成音声では、なによりアクセントが不自然な点が問題でした。この課題をクリアすることが、患者さんのより円滑なコミュニケーションを実現するカギではないかと、アクセントに加えて、骨格などの身体的特徴も加味することにしました。その結果、病前の声にだんだんと近づいてはきたのですが、ある時患者さんから思いがけないことを伝えられます。コンピュータで再生される人工音声と自身の心身の状態に大きなズレを感じると言うのです。「(この人工音声は)元気な頃の自分の声を聞いているようで辛い。むしろ、元気のない声で病気になった苦しみを理解してもらいたい」とご家族が席を立たれたすきを見計らって伝えられ、当事者の思いを想像できていなかったことに気がつき愕然としました。
[*1] 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的にかつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患である。病勢の進展は比較的速く、人工呼吸器を用いなければ通常は2~5年で死亡することが多い。
(出典:公益財団法人 難病医学研究財団/難病指定センター)
━━それは衝撃的な出来事ですね。患者さんご自身の「らしさ」とは、元気だった時の姿ではなく今の「感情」から生まれているということですね。
臨床の現場で患者さんやそれを支える言語聴覚士と関りを持てたことは、私の研究に対する姿勢にも大きな影響を与えました。基礎研究は、感情よりも理論が重要視されます。それまではクリアな音声をいかに数理的に表現することができるのかに注力していたのですが、この経験を通じて有意義な研究、つまり「役に立つこと」とは、患者さんとの「共感」なしには成立しないことが実感できたのです。そこからは、患者さんの本来の音声を再現しようとするのではなく、患者さんの状態に合わせた声、今後変化しうる声の実現を目指すことにしました。例えば、ある患者さんから「かすれた声にしてほしい」という要望がありました。決して聞こえやすい声ではないけれど、何を話しているかは理解でき、自分の感情を伝えやすいということの方がその患者さんにとっては重要だったのです。具体的には、ALSによって筋肉が徐々に動かしにくくなることを踏まえ、音声に不規則なノイズが発生してかすれたような声となるように数式をシミュレーションしていくことになりました [*2]。
その後、感情を表現できる声のひとつとして、怒りの音声を音響学的にシミュレートしたのですが、「怒り」という感情はとりわけ前後の文脈からでしか理解できないことが実験により分かりました。基礎研究において感情表現が示す特徴をどれだけ数理的に再現できたとしても、そこには限界があり、人と人とのコミュニケーションの奥深さを痛感する結果となりました。
「ごめん」という音声の物理的な特性を徐々に変化させることで、「平常→嬉しさ→怒り→哀しみ→平常」といった感情表現が実現できる。
そんな中、現場で実際に患者さんと関わっている言語聴覚士と話をすると、研究と臨床の双方に有益な着地点が見えてきます。患者さんに日々寄り添い、葛藤や苦しみ、希望や目標について共感し、それを研究者やそのほかの医療従事者と共有することが出来るのが言語聴覚士であり、研究におけるかけがえのないパートナーだと言えます。ビッグデータや機械学習を活用した音声シミュレートに関する研究はすでに始まっていますが、人対人の豊かなコミュニケーションを実現するにはまだまだ課題が多いと言えます。基礎研究と臨床・応用研究の垣根なく、相互に高め合うことが出来る本校の環境は「役に立つ」言語聴覚士養成に大きく寄与できるものと確信しています。
[*2] 慶應義塾大学川原繁人教授らとの共同研究
「マイボイス:難病患者様の失われる声を救う」としてまとめられ、2016年に日本音声学会より学術研究奨励賞を受賞した。

大阪保健医療大学大学院では、基礎研究と臨床研究を往復しながら、より高度で専門的な特論演習や特別研究に取り組む医療技術者の育成もおこなっています。
(文=浅野翔/デザインリサーチャー)
| ※関連記事 [インタビュー] 社会で活躍するOHSU|テクノロジーがひらくコミュニケーションのきっかけ https://st.ohsu.ac.jp/st-magazine/special-kawabata-wada/ |