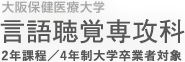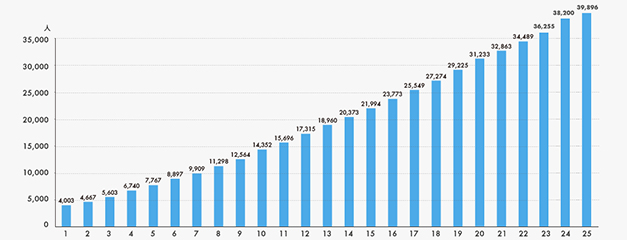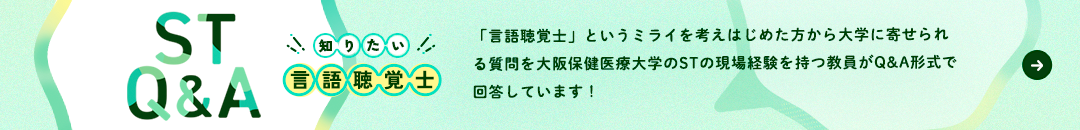INTRODUCTION
「人の役に立つ言語聴覚士の輩出」を掲げる大阪保健医療大学 言語聴覚専攻科では、様々な領域で活躍する多様な講師陣が在籍する。言語聴覚士の経験を生かし、他領域との連携により斬新な臨床活動をする柴本 勇(しばもと いさむ)氏もその一人だ。
より効果的なリハビリテーションを行うためには、確定的なセオリーに加え、患者様一人ひとりに合わせたオリジナルな方法論を導き出す力が求められる。私たちが患者様と直接会える時間は限られている、だからこそあらゆる力を結集してその空白の時間を埋めることがよい結果を生むと柴本氏は話す。
柴本氏は、たとえば工学と言語聴覚学とを融合させることで、学問や臨床の領域拡張ができ、結果的に患者様の回復につながると説く。同時に、リハビリテーションという言葉のイメージをよりポジティブにすることを狙う。「想像すること」から「創造すること」にかえる臨床感を語る柴本氏に、領域横断的な活動の一部始終を伺った。
柴本 勇先生
聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科 研究科長
聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 言語聴覚学科 教授
福井医療技術専門学校 (現 福井医療大学) 言語療法学科卒。言語聴覚士として勤務後、University of Arkansas に留学。帰国後、聖隷三方原病院、聖隷浜松病院に勤務する傍ら、東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科博士課程 で口腔老化制御学を学び博士号取得。2007年より言語聴覚士の養成教育に携わる。2016年から現職。臨床・教育・研究の傍ら、職能団体や公的機関の役員を歴任。2015年~2017年 Asia Pacific Society of Speech Language and Hearingの会長としてアジア環太平洋地域の言語聴覚障害治療の発展に尽力する。2021年より大阪保健医療大学 客員教授。
1. 「なおる」とはなにか、臨床活動を通して成熟した社会を目指す
──領域横断的な活動をしてらっしゃる柴本先生ですが、言語聴覚士になったばかりの頃はどのようなことを思いながら過ごされていましたか。
私が若い頃は、言語聴覚療法の方法論確立に先輩諸氏が努力されておられた頃でした。私も実践しながら個々の改善に向けて考える、という毎日を送っていました。日々振り返りの連続でした。効果的なやり方を、患者様方と一緒に見つけていく感覚でした。
私はとにかく先輩に恵まれていました。「なおる」とは一体どういうことなのか、という本質的な部分を学ばせていただきました。治療した後、患者様がこれからの人生をどのように歩んでいきたいのか。歩んでいかれるのか。どのようにすれば患者様の希望を確実に叶えられるか。これをご家族のお気持ちも含めて考えていく。そういったことを総合的に想像していくことが重要で、それで患者様やご家族が受け入れ前向きになれることが「なおる」ということばに含まれた真の意味だと思いました。つまり、それは患者様のこれからの人生を再設計するということも含みます。「なおる」と「治癒する」という言葉には違う意味合いがあると感じます。元通りにすることか、多少の違いはあるが再設計して同じようなことができるようになっていただくことの違いでしょうか。

──患者様がどんな形でも社会活動されること、役割を持たれることを考える。「なおる」には、そういう部分も含まれているのですね。
私は高校生の時に大ケガをしてしまいました。小さいころから培ったなにもかもを手放すくらいのケガでした。
患者としてリハビリを受けた時に大切な経験をしました。それは、高校生だった私がその後の人生を自身で受け入れられるようにと、先生方が一生懸命想像し知恵を振り絞ってくださったことでした。手段よりも私の将来の方を重視して毎日訓練をしてくださいました。元通りに治癒することよりも、納得できる生活や人生設計をふたたび。その先生方のこだわりによって今の私があると思えるほどです。
そのような先生方と実践したリハビリテーションの中で、自分のためだけに生きる人生ではなく、他人のために生きる人生にしようとの考えが湧き出てきました。これこそ真のリハビリテーションだったかもしれませんね。それで、リハビリテーションの世界に飛び込みました。ある意味、困難を経験したからこそ人生の目標を明確にすることができたのかもしれません。そして、人との出会いの重要性を今も感じています。「なおる」という感覚も、自身の患者体験から得ていると思います。
──とても大きな人生の転機だったのですね。ご自身の生の体験を通じて、日々臨床の現場で実践していらっしゃる。
私自身、常に患者代表だと思いながら仕事をしています。自身の経験から患者様方のお気持ちはわずかながらでも察することができます。そして、いくら病気やケガをしようと誰でも活躍できる社会の創出というモチベーションがあります。継続して一生懸命行っていれば、いずれ必ず良い時が訪れる。それを、自分自身が実感しています。
繰り返しになりますが、人は後遺症が残るようなケガをしたり病気をしたからといって、決して終わりではないと思うのです。それでその人の人生が終わってしまうのであれば、成熟した社会と言えないのではないかと思います。ケガや病気をしても、その人が最大限に活躍できる社会が魅力的な社会と感じます。

──言語聴覚士の社会的な存在意義にもつながってきますね。
私は、目の前の人を絶対に「なおしたい」と思っています。元通りでなくても、納得でき前向きになれることです。そのためにどんな手段でも考えます。患者様は一人として同じ人はいません。決まったセオリーを学ぶことはとても大切ですが、それが全員に当てはまるということとも言い切れません。目の前の患者様のためのオリジナルの方法論を考えることは、セオリーを学ぶことと同じくらい重要なことです。また、これがこの仕事のやりがいが大きい部分です。
言語聴覚士になって三年たった時、アメリカに留学しました。理由は、自分に力が足りないことを感じたからです。アメリカで一番学んだことは、個々の患者様を大切にすることです。そして、その人がよくなるために手段を選ばないということです。アメリカの言語聴覚士は患者様との契約です。定めた目標を絶対に期間内に実現しなければならない厳しい臨床を行っています。
その環境ですとセオリー通りに行うだけでは選ばれる人にはなりません。また、大切な患者様のお役に立つことができません。だから、あらゆる方法を使って患者様がよくなる方法を見つけ出すというマインドがあるのです。
2. 臨床における"道具"の役割
──患者様のオリジナルの方法論を見つけ出すためには、言語聴覚士として自分にしかできないことを探すことも重要なように思います。柴本先生の言語聴覚士としての自分らしさはどういった部分でしょうか?
「ゼロから何かを創造する力」だと思ってます。私は、匠の職人たちにプロフェッショナルな仕事を間近で見せていただき、職人としてのプロ意識を吹き込んでいただいたという経験があります。そのとき、職人の仕事に対する厳しさと常に最良の結果を示す重要性を身をもって学びました。
医療現場では、ゼロからモノをつくるという発想になりにくい面がありますが、「プロの仕事」と考えると、職人と同じように臨機応変な思考、最良の結果にこだわる姿勢や努力は常に必要だと感じています。

──柴本先生は、テクノロジーを用いて数多くの機器をつくられていますね。
私たち言語聴覚士は、一人ひとりの患者様と一緒に練習できる時間が限られています。しかし、私はやはり、たくさん練習をしたい方には存分にしていただきたいと思っています。また、日本はテクノロジーが素晴らしい社会。日本の屋台骨を支えてきた他分野との融合は言語聴覚療法によい効果を生むと考えています。そんな背景から患者様に必要なものづくりを検討することになりました。
医学も、医工連携で成果をあげています。治療方法も随分変わりました。言語聴覚療法も期待したいと思います。私がアメリカに留学した1990年代前半に、留学先の大学とアメリカのIT企業が言語聴覚療法の機器応用について実証研究を行っておられました。その時から、私は多領域の融合のすばらしさを見ていました。患者様のために多くの専門家が知恵を出し合い、解決する姿は素敵です。
これは、発音や発声の訓練をするアプリケーションです。スマートフォンやタブレットに向かって発音すると、正確に認識できたか否かを表示してくれます。データベース化され、正しい発音を学んでいくことができます。
これは応用版です。楽しみながら頑張れるように、遊びの視点を入れました。先程のアプリケーションを使ってロボットボールを動かすことができます。正確に発音することができたらボールが動く。楽しみながら一生懸命するうちに、だんだんと発声がうまくなっていくというしくみとなっています。
これは患者様ではなく、言語聴覚士に向けて既存の技術を応用したものです。経験が浅い言語聴覚士と熟練の言語聴覚士の視線を可視化しました(動画の例は経験が浅い言語聴覚士の視線)。患者様に食事の介助をする際、何に注意すべきかを可視化することができます。そうすることで、熟練者が経験によって身につけたスキルがどういうものなのかが分かります。ちなみにこれは「患者様を見る」か「自分を見る」かの違いです。熟練者は患者様のことをしっかり見ていますが、経験が浅い人は自分の手元ばかりを見ています。責任持った臨床とは、安全・安心・効果ある活動と思います。主体は患者様にあるはずです。
嚥下障害の方の訓練では、喉を動かす筋肉を鍛えることや、飲み込み方を工夫して患者様がご自分で実践できるようになることが必要です。しかし、どのように鍛えればよいか、どういう飲み込み方が良いかという感覚は、すぐに自分でわかるようになるわけではありません。この機器は、自分が行った飲み込み方や運動が良かったかどうかを視覚的なフィードバックでわかるようにしたものです。ランプによって正しく運動できたかどうか、飲み込み方がよかったかどうかが分かります。
大阪保健医療大学大学院では、基礎研究と臨床研究を往復しながら、より高度で専門的な特論演習や特別研究に取り組む医療技術者の育成もおこなっています。
(文=片山達貴/映像作家)
| ※関連記事 [インタビュー] STの未来を拓く|「想像」から「創造」へ。創造性が臨床力を成長させる [後編] https://st.ohsu.ac.jp/st-magazine/special-shibamoto-part2/ |