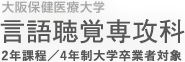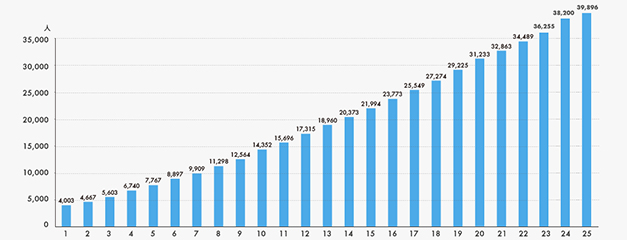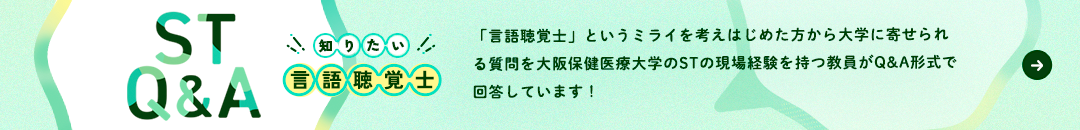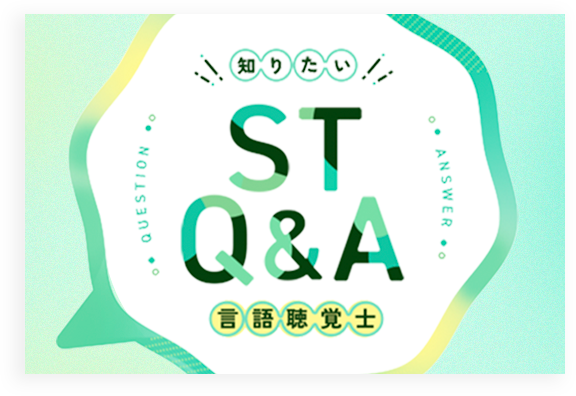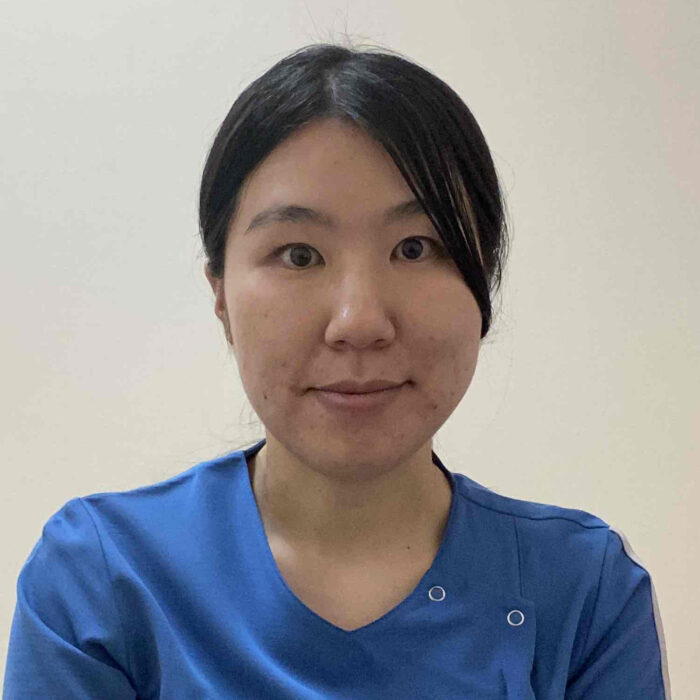
奥村 郁絵(おくむら・いくえ)さん
公立豊岡病院組合立 豊岡病院 言語聴覚士
近畿大学卒業後、大阪保健医療大学言語聴覚専攻科入学。修了後は、公立豊岡病院リハビリテーション技術科に勤務し、小児から成人の方の言語聴覚療法に携わっている。※取材当時
INTRODUCTION
発声発語器官の形態異常によって、発音がうまくできない状態を器質性構音障害といいます。
成人の器質性構音障害は、例えば舌がんに対する外科的治療のような発声発語器官の欠損が原因となって起こります。小児の器質性構音障害の代表的なものは口唇口蓋裂による発音の障害です。いずれにしても、外科的な手術と合わせて、ことばや摂食嚥下の問題への対応が必要です。また、口腔外科を専門とする歯科医、耳鼻咽喉科医、形成外科医、言語聴覚士など多職種の専門家が協力して、チーム医療で継続的に治療を進めて行くことが求められます。
口唇裂や口蓋裂は、口腔や上顎に発生する先天的な形態異常です。まず直面する問題は、ミルクや食べ物を口の中に取り込むことや、上手に飲み込むことができないことです。
リハビリテーションでは、口腔内の形態異常を補う補綴装置を作成し、食べ方の工夫や口の中の感覚に慣れてもらう練習をしていきます。成長とともに「言葉」や「発音」に問題が生じた場合は、それらの練習も行っていきます。
ご飯を食べる準備を整える
A君とは生後数ヶ月の時に初めてお会いしました。口唇口蓋裂のため唇と上顎に裂け目があり、離乳食を食べることが難しい状態でした。
手術を受けるまでの間に、口腔内の裂け目を一時的に閉鎖する補綴装置を作成し、リハビリテーションでは口の中を優しくマッサージして舌や頬をそっと刺激することを続けました。口の中に食物を含む感覚に慣れていくためです。そして、最初はミルクを飲む練習から始め、少しずつ食べる練習を行っていきました。
その後、A君は、唇と上顎の裂を閉じる手術を受け、ご飯もしっかり食べることができるようになり退院されました。
・・・・この続きは下記の冊子をご覧ください。
STをもっと知りたい方は冊子でも
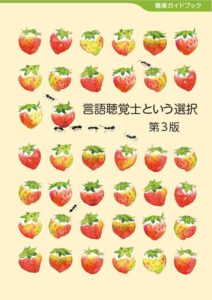
「言語聴覚士という選択」第3版(製作:大阪保健医療大学 言語聴覚専攻科)
この記事の引用元にもなっているこの冊子は、言語聴覚士という職業を知っていただくために作られました。言語聴覚士という選択。その先に何が見えるのか、ぜひご覧ください。この冊子をお読みになりたい方は、言語聴覚専攻科のイベント(オープンキャンパスなど)にご参加ください。