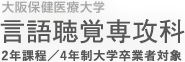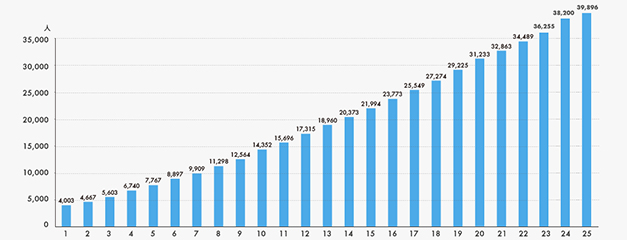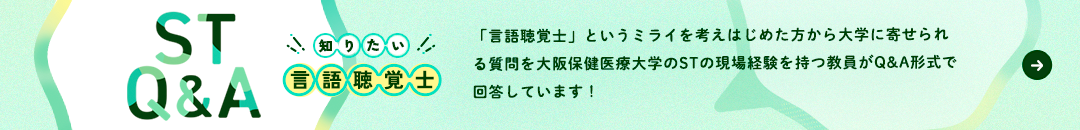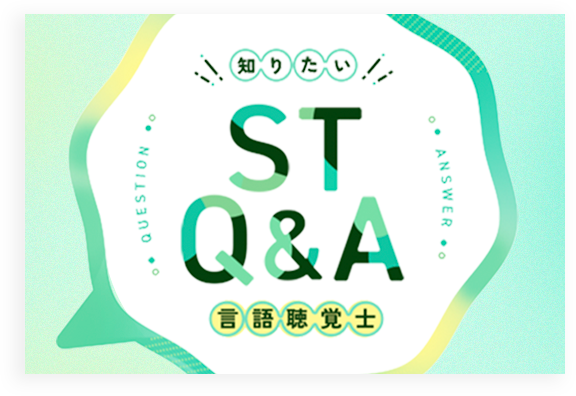不破 花梨(ふわ・かりん)さん
言語聴覚士
同志社大学卒業。大阪保健医療大学言語聴覚専攻科修了後、社会福祉法人わかたけ福祉会 丹波篠山市児童発達支援センターで勤務。※取材当時
多様な子どもたちの成長に 喜びを感じる
「そっか、前は卵のアレルギーがあったけど、今はもう食べられるんだね。」
A君のことばを繰り返すと、A君の表情がパッと明るくなりました。出会った頃のA君は、発音が不明瞭で自分が言っていることが他の人に伝わりにくいため、おしゃべりをすることに自信がありませんでした。口数の少ない子どもさんでしたが、ことばの教室を利用していただく中で"伝わった"経験を積み重ねたくさん話してくれるようになりました。
また、3歳の頃には「さようなら言わへん!」と頑なに挨拶を拒んでいたB君が、初対面の職員にも自分から挨拶や自己紹介をする姿を見て、保護者の方と改めて成長を振り返ったこともあります。子どもさんの成長を、保護者の方と一緒に見守り、喜び合える。小児の世界で働く言語聴覚士でよかったなと感じられるのはこんな時です。
丹波篠山市児童発達支援センターでは、社会福祉法人わかたけ福祉会が、丹波篠山市からの委託を受け、市内の幼児から高校生までの、発達障害、構音障害、吃音・流暢性障害、言語発達の緩やかな子どもさん等に対する支援を実施しています。市が発行する通所受給者証は必要になりますが、医師による診断等は必須ではなく、本人やご家族の方に困り感があり、職員が面談で支援が必要と判断すれば利用が可能です。子どもたちへの直接支援として、就学前の幼児を対象とした発達支援保育、言語聴覚士が担当することばの教室、作業療法士による作業療法教室、SST(ソーシャルスキル・トレーニング)教室などがあります。また、ペアレント・トレーニングや保護者学習会などの家庭支援、子どもたちの通園・通学先である園や小・中学校への訪問支援事業等も実施しています。

遊ぶことは、学ぶこと
実際の支援では、遊びの中で力を伸ばしていくことを大切にしています。例えば、ままごとやすごろく遊びをする中で数の概念を育てていきます。
低年齢や、未発語の子どもさんに対する支援は、保育士の先生から学ばせていただくことも多くあります。尊敬する言語聴覚士の先輩が保育士資格をお持ちだったこともあり、私も就職後に保育士資格を取得しました。子どもさんの支援は一人で考えるのではなく、保育士・作業療士・言語聴覚士など、それぞれの視点や考えを持ち寄ってチームアプローチを進めています。
"させられる"のではなく、子どもさん自身が"したい"と思える活動が提供できるよう心がけています。また、自己選択・自己決定できる力をつけていってほしいとの思いから、毎回遊びの一部は子どもさん自身に決めてもらうようにしています。ことばで伝えることが難しければ、写真カードや実物を見せて選んでもらいます。カードを渡す、手を引っ張るなど、自分から発信することで、楽しい経験ができることを繰り返し伝えていきます。
楽しみながら"できた"経験を積み重ね、子どもさんの自信を育てる、そんな言語聴覚士を目指して、今後も努力していきたいです。
STをもっと知りたい方は冊子でも
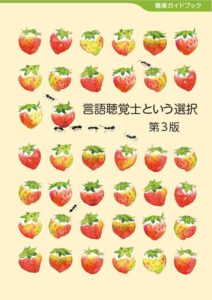
「言語聴覚士という選択」第3版(製作:大阪保健医療大学 言語聴覚専攻科)
この記事の引用元にもなっているこの冊子は、言語聴覚士という職業を知っていただくために作られました。言語聴覚士という選択。その先に何が見えるのか、ぜひご覧ください。この冊子をお読みになりたい方は、言語聴覚専攻科のイベント(オープンキャンパスなど)にご参加ください。