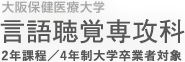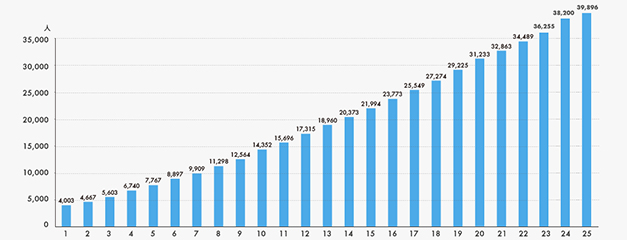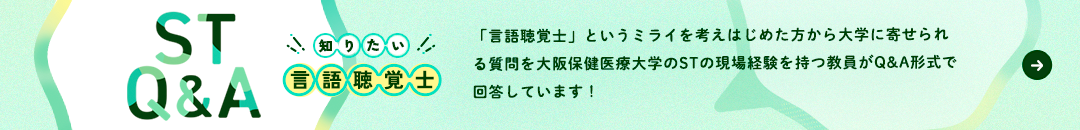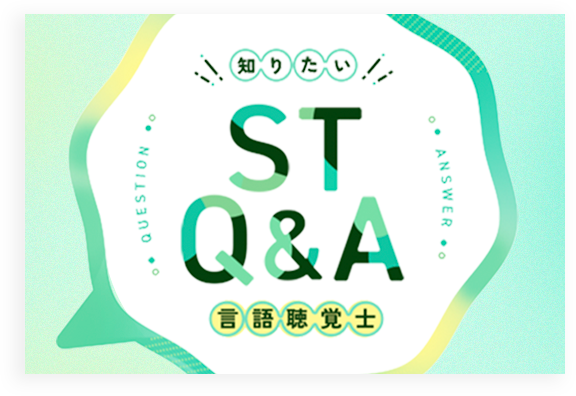森 和美(もり・かずみ)さん
言語聴覚士
筑波大学卒業。十数年の一般企業勤務を経て、大阪保健医療大学入学。卒業後は小児医療専門の総合病院や児童発達支援事業所、地方自治体での言語相談員を兼務し、小児領域の言語聴覚士としての業務に携わっている。※取材当時
INTRODUCTION
機能性構音障害とは、発語に関わる器官に麻痺や形の異常などの問題がないにもかかわらず、上手く発音ができないことをいいます。通常、小さな子どもは、上手に発音ができません。成長に伴って徐々に発音が上手になってくるものです。しかし、ほとんどの子どもが大人と同じように発音する時期になっても上手く発音できず、一部の音が別の音のように発音されてしまう場合があります。そのため話の内容が伝わりにくくなったり、話すことが不安になったりすることがあります。
発音に対する"違和感"を探る
「さ・し・す・せ・そが言えないんです」、「子どもが何を言っているかわからなくて…」、「子どもが言っていること、私はわかるんですが他の人には通じなくて…」。ことばの発音に問題をもつお子さんの保護者の方からの不安は様々です。
保護者の方が感じているわが子の発音に対する"違和感"がどこからくるのかを探すのがまずSTの大事な役目になります。
ことばの発音に関わる器官(口や喉)の形態異常や麻痺等が無いか、お子さんが言語室で遊んでいる様子、質問に対する答えは年齢相応であるか、そして保護者の方から聴き取った乳幼児健診・保育園・学校でのエピソード、構音(発音)運動の検査や発達検査の結果などの情報を基に原因を考えます。
さらに、お子さんが自分の発音の誤りに気づいているか、周囲の人々がどの程度不便を感じているかなども聞きとり、訓練の開始の時期や頻度を決めていきます。お子さんの年齢や、保護者の方の訴えの強さにとらわれて、時期尚早に訓練を開始してしまうと、本来必要のない時間や負担をかけることになりかねません。適切な情報収集とそれに基づく慎重な判断が求められます。こういった経験の積み重ねを次の臨床に活かせるところにSTの醍醐味があると感じています。
また、入り口は発音の訴えでも、実は発達がゆっくりだったり、発達になんらかの偏りがあったりするお子さんも少なくありません。ことばの問題は保護者の方や周囲の人が気づきやすく、相談もしやすいようです。いきなり「発達相談」は怖いけど「ことばの相談」なら、と言われる保護者の方も多いと学校の先生方からお聞きします。
そのようなお子さん達には、発音の訓練に入る前に、あるいは訓練をしながら、保護者の方と相談を重ね、適切な支援につなげていくこともSTの大事な役割になってきていると感じます。保護者の方と信頼関係を築き、ことば以外に気になることも相談してくださることがあります。お役に立てた時は嬉しいですし、私自身、保護者の方から学ぶこともたくさんあります

楽しい時間を過ごせるように
実際の訓練では、発音練習の合間にパズルや簡単なゲームを取り入れながら反復練習をしたり、はまっているゲームや好きなキャラクターの話で一息ついてもらったり、お子さん達が少しでも楽しい気持ちで訓練に向かえるよう心がけています。子ども達の間で流行していることについて知らな過ぎるとお子さんにつまらないと思われてしまいますので、子ども社会のトレンドの情報収集は欠かせません。この辺りは、養成校時代に尊敬する先生がおっしゃった、「STも接客業。楽しいとか、来てよかったとか、得したとか。とにかくもう一回来たい、と思ってもらうように毎回の訓練を工夫すべき」という言葉を忘れないようにしています。
出来なかった音が発音できるようになり、「もう『かきくけこ』って言える!」、「友達にいじわる言われなくなった!」と満面の笑顔で報告してくれるお子さん達。まだまだSTとしては未熟で勉強の連続ですが、発音のことでちょっと自信を無くしているお子さん達が、少しでも元気になり、自信を持って日々の生活が送れるお手伝いが出来るよう、尽力していきたいと思っています
STをもっと知りたい方は冊子でも
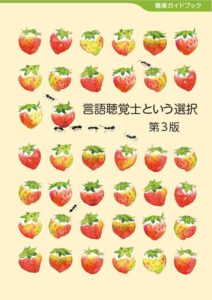
「言語聴覚士という選択」第3版(製作:大阪保健医療大学 言語聴覚専攻科)
この記事の引用元にもなっているこの冊子は、言語聴覚士という職業を知っていただくために作られました。言語聴覚士という選択。その先に何が見えるのか、ぜひご覧ください。この冊子をお読みになりたい方は、言語聴覚専攻科のイベント(オープンキャンパスなど)にご参加ください。