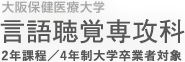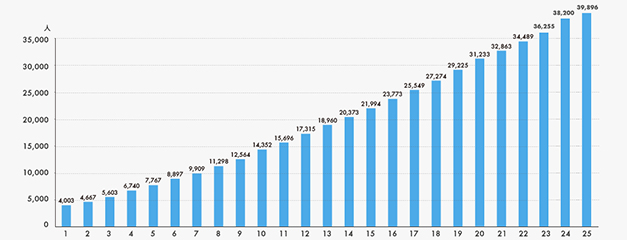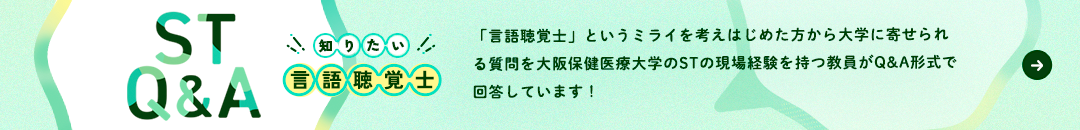和田夏実 [インタープリター]
ろう者の両親のもと、手話を第一言語として育ち、大学進学時にあらためて手で表現することの可能性に惹かれる。慶應義塾大学大学院修了後、現在は視覚身体言語の研究をおこないながら、さまざまな身体性をもつ人々と協働し、それぞれの感覚を共に模索するプロジェクトを進めている。2016年度未踏IT人材発掘・育成事業「スーパークリエータ」認定ほか。
川畑武義 [言語聴覚士]
2012年、大阪保健医療大学言語聴覚専攻科修了。2018年、同大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 脳神経疾患身体障害支援学領域に進学し、現在に至る。言語聴覚士として、重症心身障害児らのリハビリテーションをおこなう。
小児を対象としてリハビリをおこなう言語聴覚士の川畑武義さん(2012年卒)は、さまざまなツールを活用しながら、子どもたちのことばを引き出す試みを続けている。ろう者の両親のもと、手話を第一言語として育った、デザイナーの和田夏実さんの目に言語聴覚士の試みはどのように映ったのだろうか。「コミュニケーション」をキーワードに異なる領域で活動する両者の対談を収録した。
電動車いすとコミュニケーションの関係
和田|私は大学院で視覚言語としての手話を映像化することで、手での表現を引き出すツールのデザインを研究していました。今は、手話通訳だけではなく盲ろうの方の触手話での通訳など、感覚を中心にしたコミュニケーションに関わっています。川畑さんは言語聴覚士として、また大阪保健医療大学大学院でどのような研究に取り組まれているのでしょうか。

川畑|僕がリハビリテーションをおこなっている子どもたちの中には、語りかけても反応がはっきりしない、反応はあるけれどその意図が読み取りづらい子がいます。言語聴覚士として、それぞれに応じたコミュニケーション手段の確立を目指し試行錯誤する毎日です。大学院では、こうした子どもたちのコミュニケーションを促す手段のひとつとして、電動車いすの活用方法について研究をおこなっています。
僕が使用している電動車いすは、モーターやマイコン、スイッチ類がセットで3万円程度と比較的安価な「DIY版 Baby Loco」というものです。その分、座席や躯体は自作する必要があるんですが、僕は座位保持装置として市販のシャワーチェアを使い、座席の角度が調整できるようにしています。また、操作盤のスイッチやジョイスティック(スティックを前後左右に倒すことで操作がおこなえる)も取り替えることが可能です。


和田|スイッチを変えることでコミュニケーションのトリガーがどう引かれるのか観察しているということですね。
川畑|僕が見ているお子さんのひとりに、18トリソミー症候群[*1]の3歳のお子さんがいるんですが、日ごろお母さんがあやしてもあまり反応がなく、自発的に何かすることはないと思われていました。ご両親は我が子に楽しむ経験をさせられないか試行錯誤されていて、僕も何かきっかけになるものはないか探っていました。
そんな時、シーツを使ったブランコ遊びなど体が大きく揺れると反応があることに気がつき、電動車いすに乗せてみたんです。振動やモーター音、変わる風景が理由なのかは分かりませんが、とにかく外部からの刺激に反応している様子が観察されました。その後、何度か繰り返すうちに自分の体を動かしてジョイスティックを押し、車いすを動かそうとするようになりました。
そんなお子さんの姿を見て、ご両親は楽しんでいるようだと喜んでおられました。そのお子さんが外の世界とつながる可能性があると確認できた喜びでもあったと思います。
和田|子どもの力を引き出すために研究ではどのように取り組まれているのでしょうか。
川畑|脳画像と子どもの反応を照らし合わせながら仮説を立て、子どものできることを予測し、活動の幅を広げることができないかと考えています。先ほどの例だと、ジョイスティックを長いものに変えることで、手や頭で触れることができました。脳画像を見ても、視覚的に認知できれば、操作も可能だということが示唆されています。これらを踏まえると、このお子さんは自分の行動によって引き起こされる反応を学習することが出来ると言えるでしょう。
和田|自ら行動することが、学習の中できっかけを与えているのかもしれませんね。
川畑|きっかけや手掛かりがあれば学習できるということを、常にそばで支えるご家族にも気づいてもらうことが大切です。子どもの取り組みを観察・記録し、ご家族と共有することで、毎日の生活の中でのきっかけや気づきが増えていくんですね。
和田|私は研究段階で、盲ろうの子どもたちとさまざまなセンサーを用いて実験したり、その使い方をエスノグラフィックな手法で調査分析することもあります。川畑さんはどのように子どもたちの変化を記録、観察しているのですか。
川畑|普段の臨床では一瞬を見逃さないように観察することが大前提となりますが、今は研究の一環として、ご家族の同意を得たうえで、リハビリテーションの様子をビデオ撮影しています。想定された反応が得られなかった時に録画を見返すことで、座布団の置き方や、スイッチの向きなど細かな違いに気づき、検討できるという点は大きいですね。
[*1] 18トリソミー症候群
常染色体異数性の染色体異常症で、18番染色体全長あるいは一部の重複に基づく先天異常症候群である。出生児3,500~8,500人に1人の頻度で見られ、女児に多い(男:女=1:3)。90%の胎児には先天性心疾患が見られ心室中隔欠損症、心内膜床欠損症、単心室、総肺静脈還流異常症などの重篤な心疾患、ファロー症候群といった合併症を伴うことがしばしばである。これらの先天性心疾患の度合が胎児の生命力に重要な影響を与える。ごく稀ではあるが腎臓、肝臓に悪性腫瘍を合併することが報告されている。
コミュニケーションのスイッチをみつける
和田|子どもたちの微細な表現にいかに気がつくことができるのかが重要ですよね。とあるパフォーミングアーツのワークショップで、CHARGE症候群[*2]で盲ろうの少年のコミュニケーションをサポートしていました。

そのワークショップでは聖書をもとに〈神が天と地をつくられた〉という一説を表現することになったんです。他の人が地面や空を指さしたり表現している中で、彼は鳥が地面に着地するシーンを演じすることで、「神」という最小限の手話と着地の動きでそれを表現したのです。彼の細やかな動きの中で、「飛んでいる様子」や「着地」を表したことを感じとるには、時間をともに過ごし、イメージを一緒に探るということが必要になってきます。一方的に押し付けるのでなく、細かなインタラクションをくり返し互いに読み取るという点で言語聴覚士の観察力と共通しているかもしれません。
川畑|臨床ではさまざまな手段を提案することが多いので、僕も押し付けにならないように気をつけています。ひとりとして同じ子どもはいませんし、抱える障害もご家族の在り方も異なるので、気づきを得るたびに、「今のこの表情、楽しんでいるのでしょうか?」などとご家族に確認するようにしています。そうすることで、言語聴覚士とご家族の感性を高め、次にどのような提案ができるかを見極められるのだと思います。
▲和田さんが開発を手がけた視覚身体言語作成・収集ツール「Visual Creole」では、身体的な手話の映像的表現を解析し、手の動きに対して視覚表現が重なることで頭の中のイメージをより豊かに伝えることができる。
[*2] CHARGE症候群
Coloboma(眼の異常), Heart defects(心臓の異常), Atresia of choanae(口腔と鼻腔のつながりの異常), Retarded growth and development(成長や発達が遅いこと), Genital abnormalities(性ホルモンが不十分であること), and Ear anomalies(耳の異常)の頭文字より名付けられた症候群。必ずすべての症状があるわけではないが、これらの症状の多くをもつことを特徴とする。
テクノロジーとコミュニケーション
和田|私は子どものころから手話に慣れ親しんできました。在学中は、手話という視覚的な身体言語と、テクノロジーを合わせて、楽しく伝わりやすいメディアのデザインに取り組んでいました。川畑さんは電動車いすなど新しいテクノロジーを活用してリハビリをおこなっていますが、どうしてそのような取り組みを始めたのでしょうか。
川畑|電動車いすをリハビリに活用していると聞くと、理学療法や作業療法の領域だと思われるかもしれませんが、僕はコミュニケーションを促進するツールとしての可能性を感じています。海外では、リハビリの一環として電動車いすをはじめとする乗り物を活用する取り組みがおこなわれています。子ども自らが、スイッチやレバーを操作し、行為と環境の相互作用を学習することでコミュニケーション力の向上につながると考えられているからです。
電動車いすのほかにも、最近では特別支援学校などで学習支援に使われる、視線で入力するアイトラッキングという技術を使うことがあります。視線で遊ぶことのできる簡単なゲームを通じて、これまで難しかった他者との関わり合いを持ち始めるんです。生きていく上で何より大切なこのコミュニケーションを少しでも豊かなものとするためには、あらゆる方法を試していく必要があります。テクノロジーはその選択肢を大幅に広げてくれるので、臨床と研究の両場面でその可能性を確かめていきたいと思います。
和田|言語聴覚士さんだけでなく、テクノロジーに明るいエンジニアやデザイナーと一緒に発見できる環境をつくることができるといいですね。これからの大学は専門性を深めるだけでなく、領域を超えたコラボレーションを受け入れる場として機能していくのかもしれません。
川畑|そうですね、まずは学生たちにはこういう世界があるということを知ってもらえたら嬉しいですね。今取り組んでいるような研究は、卒業して臨床の場を経験したことが大きく役立っていて、大学院という受け皿があったからこそ、言語聴覚士の専門性をより深める機会を得られたのだと思います。
リハビリテーションとデザインという異なる専門性をもつ両者でありながら、その対談からは、テクノロジー/ツールを援用することでコミュニケーションのきっかけをつくり、家族や開発メンバー間での関係を構築するという共通点が発見された。そのきっかけとしての新たな道具を模索する川畑氏と、共感覚をより刺激するメディアデザインを模索する和田氏の試みからは、創造的な発想力と領域を横断する学際性を感じた。
川畑氏のように実践の積み重ねを研究として深めたいと考える者にとって、大学院での学びは言語聴覚療法を極めていく活動そのものだ。さまざまな領域で活躍する言語聴覚士の可能性はさらに広がっていくのだろう。

(2019年3月9日、graf studio kitchenにて。文=浅野翔/デザインリサーチャー)