
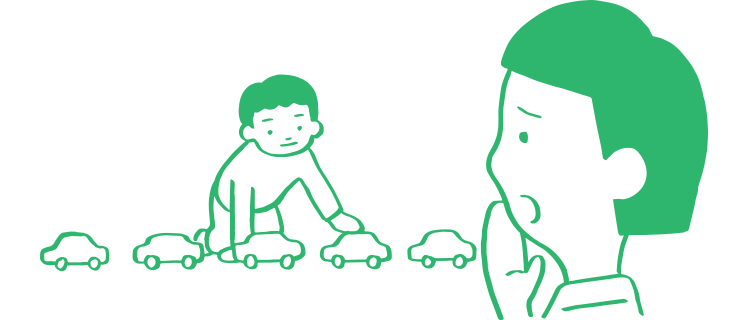
先天性の特性によって、
他人との「社会的な関わり」に
さまざまなズレを引き起こします。

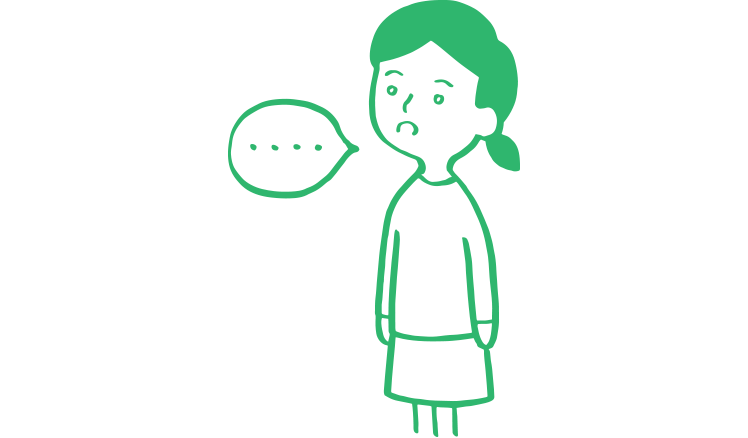
じっとしていられない、
順番が待てないなどの、
「注意」や「行動」の
コントロールが苦手です。


知的な遅れや
視力・聴力の低下がないにも関わらず、
聞く、話す、読む、書くなどに
困難が現れます。

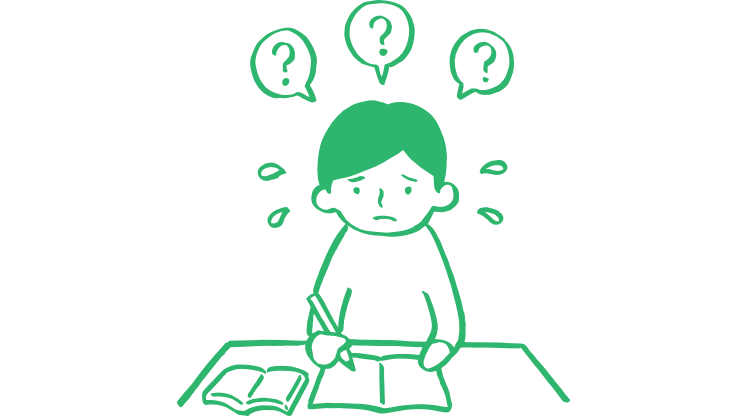

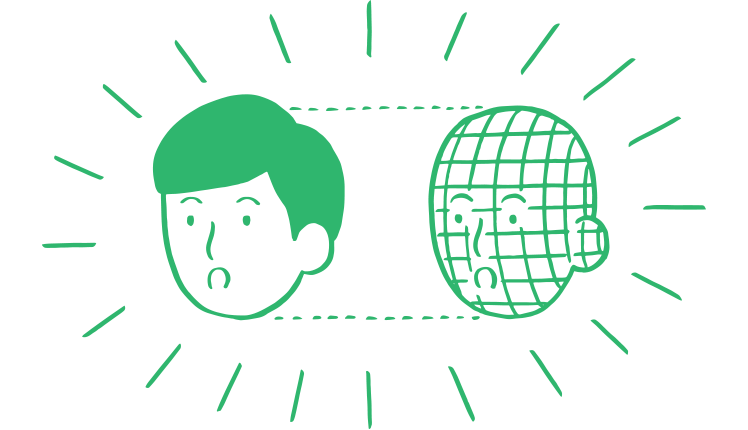

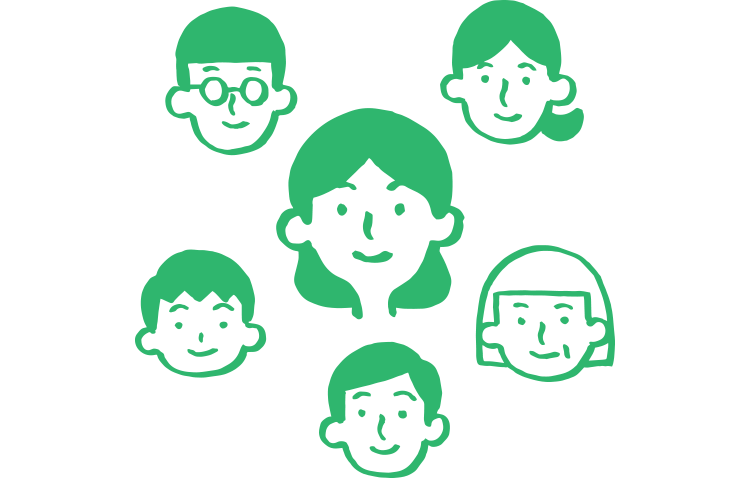
子どもでも大人でも、発達障害特性のある人の場合、失敗を咎めたり反省させたりすることよりも、できたことを認める、褒める、どうすれば良いかを伝える、一緒に考える姿勢が重要です。ただし、それは至れり尽くせりで「転ばぬ先の杖」を周囲が“過剰に”用意することとは違います。大なり小なり人は間違いも失敗もします。それらが「ダメなこと」というメッセージばかり伝えないことです。安心できる環境で失敗し、立ち直り、問題解決をしていく中で、コミュニケーションの力や社会性も伸びていきます。例えば、その場所は遊びの中や学校生活、家庭生活です。そして、その子・その人なりの学び方や考え方のスタイルを尊重することが必要です。


区市町村の子育て支援や障害福祉の窓口で、地域にある療育機関やサポート機関について問い合わせましょう。医療機関では、小児神経科医や児童精神科医、発達障害に詳しい小児科医などを受診します。また、臨床発達心理士、臨床心理士など心理を専門とする職種や保健師、作業療法士、言語聴覚士などの専門職、保育士、社会福祉士、スクールソーシャルワーカーのような福祉職が各種の相談、療育・指導・訓練に関わります。特定の理論や技法による療育を進めている大学や民間施設もあります。診断の有無に関わらず、相談機関を利用して問題を一人で抱え込まないことを強くお薦めします。